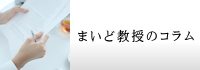私は過去40年間近くにわたり、中小企業を訪間してきました。「まいど―」の掛け声とともに、ほぼ3日に一度の割合で続けた結果、顔なじみになった中小企業経営者も多く、いつしかクまいど教授クのエックネームで呼ばれるようになっていました。これまでに訪れた企業は、とても数えきれません。
最初は東大阪ならびにその近辺が主体でしたが、大学の研究員として、また中小企業事業団(現・中小企業基盤整備機構)の産業集積地研究班員として、テレビ番組の講師としても各地を訪ねる機会が増えていきました。さらに、共同通信社の政経懇話会のメンバーとして各地で講和を行い、その都度、地域産業の状況を視察してきたのです。本レポートは、このように私自身が実際にこの足で現地へ赴き、この眼で現場を見て、この耳で経営者の声を聴いたからこそ知り得た知見を皆さまに披露するものです。
地場産業が再生へ向かうための”4つの戦略“
日本国内には中小企業集積地が300以上あるとされています。そのほとんどが地場産業を形成しており、地域の経済はもちろん日本経済の発展にも大きな影響を与えてきました。ところが市場のグローバル化が進む今、需要・供給ともに新規参入が容易となり、地域に根付いた中小企業の競争力は軒並み低下。地場産業は存立基盤が問われているとさえ言われています。
果たして地場産業は本当に過去の遺物となってしまったのでしょうか。私はこうした悲観的な考えに疑間を抱いています。若者が中心になって再生に向けた戦略を展開し、成功している地場産業を私自身がいくつも知っているからです。
その戦略の第一は「モノからコトヘの転換」。第二は「自社が持つ地財、すなわち自社の強みの掘り起こし」。第三は、「お客様の立場で再度見直す」。第四は「ネットワークの再構築」です。本稿では特に、二番目に挙げた「地財活用」の具体例をご紹介します。
3名の若者のベンチャー企業が気づいた地財
最初の舞台は大阪・泉州地域。大阪市から関空周辺までのエリアを指しています。明治期以降に輸入綿を用いた紡績工場が立ち、タオルや織布、毛布、敷物、ニットなどの産地として発展してきました。タオル産業発祥の地とされており、大阪の繊維問屋や商社に近いことも順調にシェアを拡大してきた理由です。
しかし近年、問屋や商社が次々に海外へ進出したことに伴い、取引高が激減してしまいました。心ない批評家からは不況という熔印を押され、再生のめどはないといった声があちこちから聞こえてきます。
泉州地域の地場産業は、かつての栄光を取り戻すことはできないのだろうか。独自に検証をはじめた矢先、ふとした縁で出会ったのが「株式会社クレツシエンド」という企業でした。T」のままではニット産業は衰退して消えてしまう」と危機感を持った大手ニットメーカー3社の二世たち、わずか3名で立ち上げたベンチヤー企業。取扱商品は横編ニット製品、丸編ニット製品、布鳥製品などがあり、これらの製品の企画・生産を通してOEMを中心にオリジナルブランド製品も世に送り出しています。
繊維製品において編む作業を担当するエット産業は、製造工程の出口にあたる分野であり、産業麦退の影響が最後に及ぶところです。同社設立のきっかけは、「この(ニット)産業が元気なうちに新たな飯の種を探そう」というものでした。
下請けからの脱却を狙う同社が目標に据えたのは「企画提案できる企業」になることでした。とは言え、先行投資は極力抑えたい台所事情であり、外部の一流デザイナー起用においても負担が少ないよう3社で費用を分担したそうです。かくして、デザインのプロと繊維のプロが協働したデザイン案が完成。大手アパレルメーカーにアプローチを試みました。今わの際と言える状況から放たれた一矢は、果たしてどうなったでしょうか?
輝身の作品は大手アパレル企業に高く評価され、見事に製品のOEM生産を受注。「製品を生み出す企画」と「末端の製造」をどちらも引き受けることで、新たな活躍の舞台を見つけることに成功したのでした。
この時、同時に彼らが考えたことは、自分たちの地元の活用でした。あらためて地元を見直せば、そこは繊維産業の集積地域であり、アパレルに必要な要素技術がすべて身近に存在しています。
「洋服に必要な材料を扱う企業、縫製を行なう企業等々がすべて同じ地域に集まっており、ネットワークで結んで上手く連携できれば柔軟な対応ができる。急な大量注文や絶えず変化するオーダーヘの素早い対応も可能。これを活かすことができれば、地域がさながら一大縫製工場となる」。
こうした「地財」の存在に気づいたことによる確固たる自信が、大勝負に打って出ることへの迷いを吹っ切り、起死回生のストーリーを生み出したのです。
先述したように、クレツシェンドは今、OEM生産からさらに発展して自社ブランドを持つまでに成長。企画、製造から販売までを一貫して自らの手で行なう企業にまで成長しています。
同社の成功は、母体とも言える泉州地域にも恩恵をもたらしました。アパレル業界における産業集積地であることが再評価され、あらゆる繊維製品に対して柔軟に対応できる地域であり、また潜在的な可能性を十分に秘めていることが証明されたのです。取引先数も着実に増え続け、ほとんどの日本の大手アパレルメーカーのOEM生産を手掛けています。
二代目社長の築いた縦軸と横軸が編み出した新製品
次に紹介するのは、静岡県掛川市の染色織物メーカー「有限会社福田織物」です。この辺りは昔、糸染色工場が5社ほどありましたが、次々と廃業し、現在は1社のみとなってしまいました。生地染色の工場は8社が操業していますが、20年前の半分以下という状況です。そんな中、同社は綿100%を誇る高密度の綿織物、打ち込みのしっかりした織物を作っています。
福田織物は、長年にわたり一般的な綿生地を生産するだけの機屋に徹してきました。綿100%の加工を手掛けたことがなく、北陸地方にあるポリエステル100%の長繊維での織物を扱う加工会社に依頼していたのです。 一方、加工会社は「長繊維の面白い加工はできるが、今までポリエステル100%以外では取り組んだことがない」のが悩みでした。そこで同社は「何かユニークな工夫はできないか」と思案し、福田織物に対して、ある製品を加工前の織り上げただけの状態で送りました。具体的に言えば、「ポリエステル100%に塩縮加工」というものです。
福田織物は、それを見て非常に興味を持ち、「綿100%での塩縮加工」を依頼しました。その加工会社にとって綿は未知の領域だけに技術的なハードルも高かったのですが、2、3カ月かけて克服。非常に面白い商品ができたと自信を持って送り返したのです。受け取った福田織物の社長はそれを見て「全然違う商品を送ってきたんじゃないか!?」と思って電話をしたところ、いきさつを聞いて感激したと言います。
このようにして技術革新に取り組んできた福田織物ですが、二代目社長がある決断を下したことにより、流れが大きく変わりました。
「当社は高度な技術を有しているが、他社の主導によるものが大きい。今後はこうした状況に甘んじるのではなく、自社が主導して技術開発に取り組むことが重要である」。
二代目社長は技術の伝承という縦軸を大切にしながらも、地域問運携といった横軸の形成にも積極的に乗り出し、築いたネットワークをフルに活用することによって、糸の入手から企画・製造・販売までを実現しました。また、地域問連携の過程において「地財」の存在に気づき、かつて染色が盛んであったこの地域ならではの貴重な情報を収集。自社が中心となって技術開発に取り組み、直接的に染色とは結び付かないものの、高度な技術を集積した「光透けるストール」の製品化に至ったのです。
驚きの薄さと軽さ、肌触りを有する同製品は、綿100%でありながら、まるでシルクの心地良さ。世界全体で5%未満しか取れないと言われている貴重で上質な新彊綿を120番手という極細の糸にし、職人ならではの高度な技術によって織り上げたものです。
こうして生まれたオンリーワン商品のポテンシャルは限りなく大きく、世界のファッション界から注目を集める存在になりました。いまや国内外のアパレルメーカーに生地を販売するまでに成長を遂げたのです。
「どんなモノをつくるか」から「どんなコトに使えるか」へ
地場産業が地財の存在に気づき、効果的に活用した結果、衰退期から息を吹き返したり、好況を維持し続けている例は枚挙に暇がありません。播州織で有名な西脇市、鞄の衛で知られる豊岡市、刃物の代名詞とも言える三木市などにおいても、若手経営者は早くから将来を見据えて呆敢に戦略を立てています。その戦略こそ、将来を憂う中小企業が学ぶべき指針であり、その本質はシンプルそのものです。
それは「モノづくりにおける見方の変化」に他なりません。「どんなモノをつくるか」といった視点から、モノづくりで培ったコンテンツを「どんなコトに使えるか」。“4つの戦略”でも述べたモノからコトヘの転換であり、先述した泉州の例も同様です。彼らは繊維を追うのではなく、この地域がどんなコトを持っているか、その中身を知ることによって、「ファジーなモノづくりのメッカ」であることに気づいたのです。その意味では、繊維産業は私たちに英知を提供してくれたと言えるでしょう。繊維産業は超成熟産業であり、日本のあらゆる産業の30年先を描いているのです。
じつは、私は以前から繊維産業に着目してきました。否応なしに産業界の再編が進む中、繊維産業は衰退期にあると位置付けられ、将来性が見込めないとさえ言われてきました。しかし私は、自分自身がこれまで取材してきた中で体感した、繊維産業に携わる中小企業の底力を知っていたからです。
親方的存在の大手繊維企業や商社が海外へとシフトチエンジする中で、各地場産業が右往左往するのは当然です。しかし、時間はかかるものの自助努力でそれぞれの地財を発見し、手探りながら連携を果たしていくことで力強く再生を果たしています。
地場産業が再生へと向かうための“4 つの戦略”は私が編み出したものでは決してなく、実在する中小企業経営者ならびに従業員が実際に挑戦し、確かな成果を上げたエッセンスを、彼らに代わってまとめたものです。存立基盤を立て直すための処方箋であり、これを着実に実践していくことで、業界や規模を問わず、どの中小企業も必ずよみがえることができると確信しています。
ヒョウゴ経済 2017年10月号 No.136